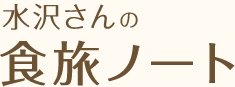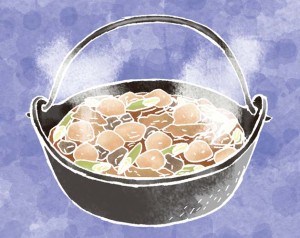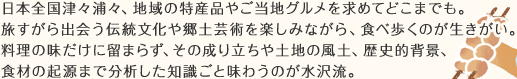
いも煮
山形県
山形の秋を彩る食の代表格
9月に、大きな鍋で「日本一の芋煮会フェスティバル」が開かれる、山形県を代表する郷土料理。地元では、秋になると家族や友人たちなど人々が集まり、いろいろな場面でいも煮を囲む光景が見られます。いも煮は、里芋を使った鍋料理。ネギ、コンニャクをはじめ、さまざまな具材が入り、内陸地方では牛肉を入れた醤油味仕立て、庄内地方では豚肉を入れた味噌味仕立てなど、地域によっても具材や味付けの仕方が異なるので、いろいろな場所で食べてみるのもいいかもしれません。
いも煮の起源は、十五夜に団子でなく里芋を供えた風習だとか、船頭が里芋と積み荷の棒タラを鍋で煮て食べたことに由来するなど諸説ありますが、江戸時代の頃に遡るといわれています。ただ、その頃は、現在のように肉を食べる習慣はまだ一般的にはなかったようです。具だくさんの汁物は身体が暖まり、楽しい会話もはずんで、みんなの心と身体を幸せにしてくれます。
関連ワード: 山形県
白石うーめん
宮城県
身体にやさしい伝統の名産品
そうめんのような細い麺で口当たりが良く、食べやすいと評判なのが「白石うーめん」。そうめんと違って、油を使わないのが特徴です。その昔、胃の病に苦しんでいた父のために、息子が旅の僧侶から油を使わない麺の製法を学び作り上げました。小麦粉と塩水で作った麺を食べた父は病が治り、人の温かい思いやりが生んだということで、この麺のことを「温麺(うーめん)」と呼ぶようになったといわれています。
今では、江戸時代からの伝統を刻む名産品として知られているうーめん。冷やしもありますが、これからの季節は温かいうーめんが特におすすめで、人気があります。お店によって、いろいろなメニューがあるので、食べ比べてみると楽しいですよ。
関連ワード: 宮城県
おこぜの唐揚げ
広島県 尾道市周辺
外見に似合わず美味な高級魚
おこぜは、見た目には、口が大きく怖い顔をしていて、突起があるグロテスクな体系の魚ですが、その身体に似合わず、ふっくらした白身が実に美味しい魚。刺身や唐揚げにすることが多いのですが、食べられる部分が以外に少なく高級魚とされています。唐揚げにすると、固い頭の部分までかぶりつくことができて、けっこう食べられる部分が多くなります。もみじおろしとポン酢で食べるのが一般的。尾道には、おこぜの唐揚げを食べることができるお店や旅館が多くあり、多くの寺院が建ち並ぶ風情豊かなこの街へ行った時には、必ずいただく、私の大好きな逸品です。
関連ワード: 広島県
ままかり寿司
岡山県
“まま”を借りにいくほどの美味
 あまりのおいしさに食が進んで、ご飯(まま)がなくなってしまい、隣の家まで借りに行って食べるほど、というところから名が付いたといわれる「ままかり」。名前の由来を聞くと、思わず食べたくなってしまいます。サッパという魚の別名で、酢漬けにして作ったのが、ままかり寿司。見るからに光っていて、美味しそうです。あっさりしているのに、噛むほどに味が広がり、本当にいくつでもいけちゃいます。
あまりのおいしさに食が進んで、ご飯(まま)がなくなってしまい、隣の家まで借りに行って食べるほど、というところから名が付いたといわれる「ままかり」。名前の由来を聞くと、思わず食べたくなってしまいます。サッパという魚の別名で、酢漬けにして作ったのが、ままかり寿司。見るからに光っていて、美味しそうです。あっさりしているのに、噛むほどに味が広がり、本当にいくつでもいけちゃいます。
岡山駅の駅弁にも並んでいるので、ぜひ食べてみてください。車窓の景色を見ながら味わうのも、旅ならではの楽しみ方ですよ。
関連ワード: 岡山県
じゃこ天
愛媛県
瀬戸内の小魚のうまみが詰まった逸品
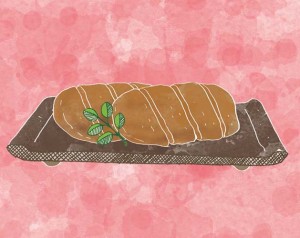 地魚の骨や皮ごとすりつぶしたすり身を、小判型にのばしたり、団子状に形を整えて油で揚げた魚肉の練り製品。瀬戸内地方を中心に、このように小魚のすり身を揚げたものを、昔から「天ぷら」と呼んでいました。小魚のうまみがギュッと詰まっており、カルシウムが豊富でヘルシーな郷土の味です。
地魚の骨や皮ごとすりつぶしたすり身を、小判型にのばしたり、団子状に形を整えて油で揚げた魚肉の練り製品。瀬戸内地方を中心に、このように小魚のすり身を揚げたものを、昔から「天ぷら」と呼んでいました。小魚のうまみがギュッと詰まっており、カルシウムが豊富でヘルシーな郷土の味です。
名前の由来は、いろいろな魚を意味する「雑魚(ざこ)」から「じゃこ天」になったとか、主要原材料となるハランボ(ホタルジャコ)から「じゃこ天」になったとか、諸説があります。スーパーの店先や食堂、居酒屋などのメニューにも並び、各お店それぞれにこだわりと違いがあって食べ比べも楽しい。値段も手頃、おやつ感覚で気軽に食べられるのが嬉しい逸品です。そのまま食べる他に、酢の物やサラダに合えたり、うどんやおでんの具としていただくのも、人気があります。
関連ワード: 愛媛県
しょうゆ豆
香川県
偶然が生んだ特産品
 しょうゆ豆は、煎ったそら豆を砂糖やしょうゆ、唐辛子のたれに漬けたものです。煮豆ではなく煎ってから漬け込んでいるから、噛んだ時に口の中でポロッと砕ける歯ごたえ。皮ごと食べることができ、皮に含まれる食物繊維も魅力です。旅館の朝食で初体験しましたが、白飯にぴったりで何粒でもいけそうです。そのまま食べても良し、野菜と一緒に炒めたり、刻んで卵焼きに入れたり、アイスに入れたり。地元ではいろいろな食べ方で重宝されています。
しょうゆ豆は、煎ったそら豆を砂糖やしょうゆ、唐辛子のたれに漬けたものです。煮豆ではなく煎ってから漬け込んでいるから、噛んだ時に口の中でポロッと砕ける歯ごたえ。皮ごと食べることができ、皮に含まれる食物繊維も魅力です。旅館の朝食で初体験しましたが、白飯にぴったりで何粒でもいけそうです。そのまま食べても良し、野菜と一緒に炒めたり、刻んで卵焼きに入れたり、アイスに入れたり。地元ではいろいろな食べ方で重宝されています。
古代エジプトでも作られていたという、そら豆。香川県では麦の間作として栽培されていたのが、特産品になったそうです。また、瀬戸内海の小豆島のしょうゆ作りは、400年の歴史を持つ伝統産業で、今も多くのしょうゆメーカーがあります。しょうゆ豆は、そんな香川県の2つの伝統の味が組み合わさって生まれた、昔ながらの郷土料理。しかしその誕生は意外にも偶然だったとか。その昔、そら豆を煎っていたら、近くにあったしょうゆ壷に豆が飛び込んでしまった。後でその豆を食べてみると何ともおいしくて、やがて広まっていったといわれています。これがしょうゆ豆の歴史の始まりなのです。
関連ワード: 香川県